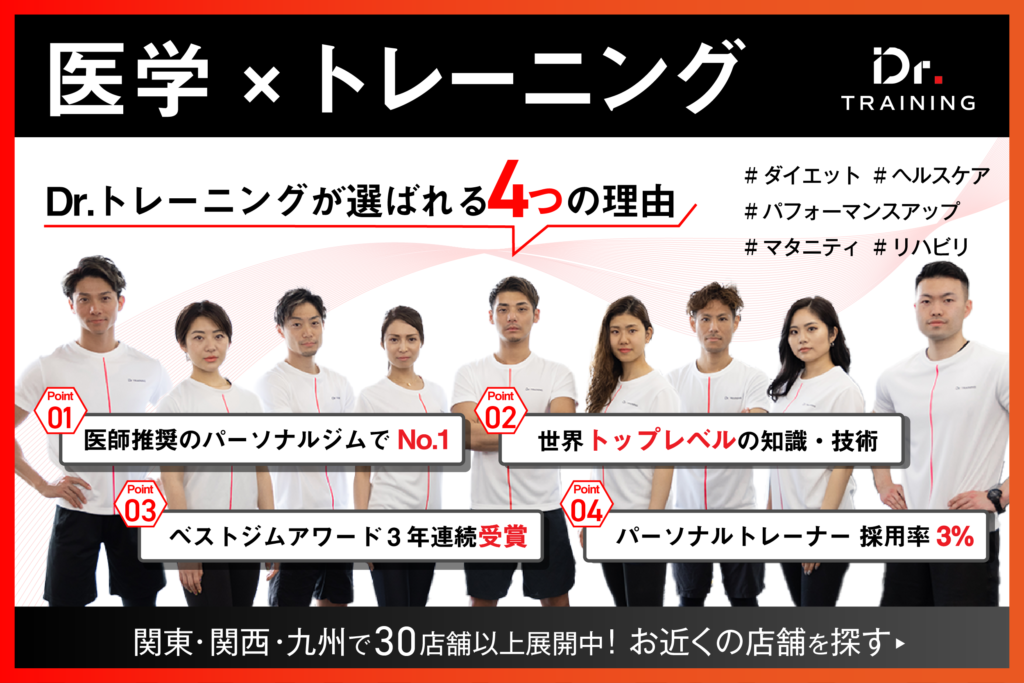2025.04.18
監修者: 代表取締役 山口 元紀
オーバートレーニング症候群について|予防やチェックすること
目次
近年、トレーニング熱が高まる一方で、見過ごされがちなのが「オーバートレーニング症候群」です。
頑張るほどに体調を崩すリスクが潜むこの状態は、早期発見と予防がカギとなります。
この記事では、その兆候や対策をわかりやすく解説します。
【この記事以外の、おすすめ記事】
記事はこちら
https://drtraining.jp/media/29384/
オーバートレーニング症候群の概要
オーバートレーニング症候群とは、運動やスポーツにおけるトレーニング負荷が過度となり、身体および精神の回復が十分に行われなくなる状態を指します。
定義としては、日常的な疲労や一時的なオーバーワークと異なり、持続的なパフォーマンス低下や慢性的な疲労感、モチベーションの喪失、睡眠障害など多様な症状が現れる点が特徴です。
オーバートレーニング症候群を予防するには、トレーニングと回復のバランスを考慮したプログラムを実践し、適切な休息を計画的に取り入れることが重要です。健康的な身体づくりとスポーツパフォーマンス向上には、オーバートレーニング症候群の理解と対策が不可欠です。
症状とその特徴
オーバートレーニング症候群の症状は多様であり、主な特徴として身体的なサインと精神的変化の両方が見られます。
身体面では、慢性的な疲労感が続き、小さな運動でも著しい疲労や心拍数の異常な上昇が現れやすくなります。さらに、筋肉の硬直や痛み、腰痛、疲労回復の極端な遅れが特徴です。
また、貧血やめまい、下痢、微熱など風邪に似た症状も現れることがあります。睡眠障害も代表的な症状の一つで、不眠や寝付きにくさ、熟睡感の不足、起床後の強い眠気が頻繁に報告されています。
精神面では、意欲の低下や集中力の欠如、不安感、イライラなど情緒の不安定さが認められ、症状が重症化すると精神状態が悪化し、うつやうつ病に似た状態に発展することもあります。これらの症状は日常生活や競技パフォーマンスの低下だけでなく、健康全般に悪影響を及ぼすため、早期の認識と適切な対応が極めて重要です。
なぜオーバートレーニング症候群が起こるのか

オーバートレーニング症候群は、なぜ起こるのかというと、その原因は身体への過度な運動によるストレスにあります。
運動を繰り返すことで筋線維の損傷や疲労が徐々に蓄積し、十分な休息を取らないままトレーニングを継続すると、身体の回復機能が追いつかなくなります。特に脳の中枢神経系が大きく影響を受けることが重要なポイントであり、身体を調整する指令が正しく機能しなくなることで、慢性的なパフォーマンス低下が起こります。
初期段階では、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌が見られ、それに伴い心拍数や血糖値が上昇するなど、身体全体にストレス反応が現れやすくなります。このような状態が継続すると、中枢神経の疲弊が進み、回復力が著しく低下します。結果として、身体が強い疲労感を感じていても、適切な回復のサインが出なくなり、長期間にわたる不調の原因となってしまいます。
このような複数の生理的異常や慢性的なストレスが重なり合うことによって、オーバートレーニング症候群が発生するのです。
スポーツとオーバートレーニング症候群
スポーツをしている方は、サッカー選手や野球選手、テニス選手、さらには陸上競技を行う選手やマラソン、ランニング、など競技力の向上を目指して日々高強度のトレーニングに取り組んでいます。
しかし、過度な練習はオーバートレーニング症候群のリスクを高め、特にサッカーや野球、テニスなどの団体・個人スポーツを問わず、シーズン中や大会前の追い込み期間は心身にかかる負担が大きくなりがちです。
疲労が十分に回復しないままトレーニングを継続すると、パフォーマンスの低下だけでなく、怪我や精神的ストレスが増加しやすくなります。特にマラソンやランニングを継続的に行うアスリートも、体調の変化を自覚せずに無理を重ねがちです。
真面目で努力家な選手ほど自身の限界を見誤りやすいため、指導者やトレーナーがサポートし、こまめにコンディショニングをチェックして適切な休養や練習量の調整を提案することが重要です。
競技や種目を問わず、選手が心身のバランスを保つためには、トレーニングと休息の調和が不可欠であり、長く安定した競技生活を送るためには定期的な休養と回復をしっかり確保することが大切です。
診断の難しさとチェック方法
オーバートレーニング症候群は、症状が他の疾病や単なる疲労と重なるため、診断が非常に難しいとされています。
特に、疲労感や精神的な不調は一般的な体調不良と似通っており、明確な診断法が確立されていないことから、専門的な検査なしには正確なチェックが困難です。
そのため、医療機関やトレーナーは選手や運動者の身体的・心理的状態を総合的に評価し、パフォーマンスの低下や日常生活における活動量の変化を細かく観察します。
具体的なチェックポイントとしては
・自己申告による疲労感の変化
・起床時の心拍数
・睡眠の質
・トレーニング内容や休息時間の記録
などが挙げられます。
これらをもとに、重症化する前の早期発見を目指し、状態を定期的に記録・評価することが重要です。
また、複数のチェック項目を組み合わせた診断法で、より正確にオーバートレーニング症候群の可能性を判断し、適切な対策を行うことが求められます。
改善の方法
オーバートレーニング症候群の改善では、まず十分な休養を取り、身体的・精神的な回復を最優先することが重要です。
過度な運動を控え、必要であれば一時的にトレーニングを中断します。ストレスを軽減するためには、リラクゼーション法の実践や適切な睡眠環境の確保が非常に効果的です。また、回復過程でリハビリを取り入れ、筋力や持久力の低下を防ぎながら徐々に活動量を増やしていくことも大切です。
食生活では、体の修復を助けるタンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することで、効果が高まります。必要に応じて、専門医と連携し、症状に合わせて心理的なサポートやカウンセリングを受けることも回復の手助けとなります。症状が重い場合には、段階的な運動負荷の調整や、医師による継続的な管理が求められます。無理をせず、専門家の助言を得ながら適切な治療とリハビリを進めることが、オーバートレーニング症候群克服への最善策です。
予防のためのポイント

オーバートレーニング症候群の予防や対策には、トレーニングと休息のバランスを適切に保つことが重要です。十分な休養時間を確保して身体の疲労回復を促すほか、トレーニング強度や量は段階的に調整し、急激な負荷の増加を避けるよう注意しましょう。
また、予防の観点から栄養バランスのとれた食事や質の高い睡眠を心がけ、規則正しい生活習慣を意識することも大切です。ストレス管理やリラックスできる時間を取り入れることは、心身の疲労対策としても役立ちます。自分の体調やパフォーマンスを定期的にチェックし、何か異変を感じた場合は早い段階で適切に対策することが効果的です。
まとめ
オーバートレーニング症候群は、過剰なトレーニングと十分な休息不足によって生じる複合的な疲労状態です。
身体的な疲労だけでなく、精神的な不調も併発するため、早期発見が非常に重要です。症状としては心拍数の異常や慢性的な疲労、睡眠障害、意欲低下など多岐にわたるため、日々の体調変化やパフォーマンスの低下に注意し、速やかに対策を講じることが求められます。
オーバートレーニング症候群の改善は、十分な休養と栄養バランスのとれた食事、ストレス管理が不可欠であり、段階的なトレーニング再開が回復をサポートします。また、予防にはトレーニング計画の見直しや、適切な負荷調整、体調管理、生活習慣の改善が効果的です。このような予防策や対策を日常的に取り入れることで、健康を維持しつつ効率良くトレーニングを続けることができます。
とはいえ、自分1人ですべてを管理して実行するのは難しいものでもあります。そんなときは、一人ひとりに合わせたメニューを提供し、3つのプランから選択できるDr.トレーニングにお任せください。医学的根拠に基づくトレーニングと食事管理で、お客様の理想に近づけるサポートを行います。
無料カウンセリングや体験トレーニングも随時受付中なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【著者情報】
東田 雄輔
– 資格
・NSCA-CPT(全米エクササイズ&コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー)
・JATI-ATI(日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者)
・NASM-PES(全米スポーツ医学協会認定パフォーマンス向上スペシャリスト)
・NASM-GFS (全米スポーツ医学アカデミー認定ゴルフフィットネススペシャリスト)
・IASTM SMART TOOLs
・PRI Postural Respiration
・PHI pilates act