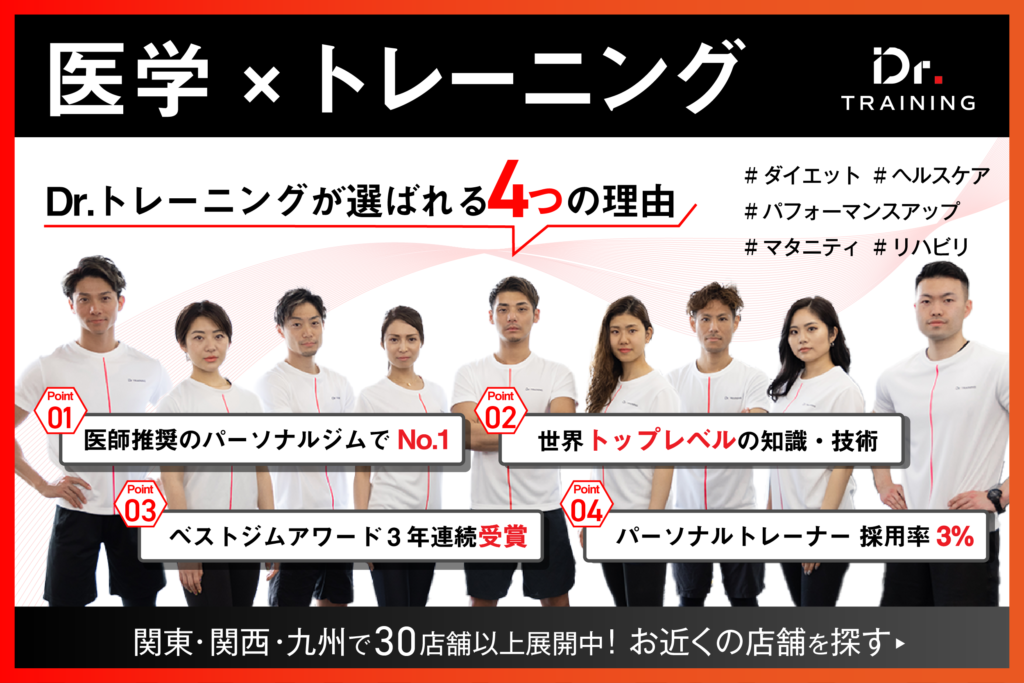2025.11.15
監修者: 代表取締役 山口 元紀
筋トレ用パワーグリップの効果的な使い方|おすすめの種目やあえて使用しないケースなども紹介
目次
筋トレの効果を最大限に引き出すためには、トレーニングギアの活用が有効です。
その中でもパワーグリップは、習熟度に関係なくおすすめしたいアイテムの一つです。
パワーグリップを使えば握力を補助できるため、本来鍛えたい筋肉を最後まで追い込むことが可能になります。
この記事では、パワーグリップの基本的な使い方から、その効果を高めるおすすめのトレーニング種目まで、分かりやすく解説します。
そもそも筋トレ用パワーグリップとは?

パワーグリップとは、ウエイトトレーニングの際に握力を補助するためのトレーニングギアです。
手首にベルトを巻きつけて固定し、手のひらから伸びるベロと呼ばれる滑り止め部分をバーベルやダンベルのシャフトに巻きつけて使用します。
これにより、握力が先に疲弊するのを防ぎ、背中などの大きな筋肉へ意識を集中させることが可能です。
一般的なトレーニング用の手袋とは異なり、特にデッドリフトや懸垂といった「引く動作」の種目でその効果を発揮します。
筋トレ効率が上がる!パワーグリップを使う3つのメリット
パワーグリップをウエイトトレーニングに導入することで、多くのメリットが得られます。
主に「ターゲット部位への集中の向上」「使用重量の増加」「手のひらの保護」という3つの側面から、トレーニング効率を大幅に高めます。
握力の消耗を防ぎターゲットの筋肉を最後まで追い込める
デッドリフトやベントオーバーロウといった背中のトレーニングでは、本来鍛えたい広背筋や僧帽筋よりも先に、前腕や指の力が尽きてしまうことはないでしょうか?
握力が限界に達すると、たとえ背中の筋肉に余力があっても、それ以上トレーニングを続けることは難しくなります。
パワーグリップを使用すると、握力を強力にサポートするため、握力の消耗を気にすることなく、ターゲットの筋肉に意識を集中させられます。
これにより、「オールアウト(目的の部位を限界まで追い込む)」までトレーニングの効果を格段に高めることが可能です。
より重い重量を扱えるようになり筋肥大を促進する
筋肥大を目指す上で、筋肉に対して漸進的に負荷を高めていく「漸進性の原則」は非常に重要です。
しかし、握力がボトルネックとなり、扱えるウエイトの重量が伸び悩むケースは多く見られます。
パワーグリップで握力を補助すれば、これまで自身の握力では扱えなかった、より重いウエイトでのトレーニングが可能になります。
筋肉はより強い刺激に適応しようと成長するため、高重量を扱えることは筋肥大を促進する上で直接的な要因となります。
手のひらのマメや痛みを予防してトレーニングに集中できる
高重量のバーベルやダンベルを素手で繰り返し握っていると、手のひらの皮がむけたり、硬いマメができてしまったりします。
こうしたマメや痛みは、トレーニングの集中力を削ぐ原因となり、時には痛みのために全力を出し切れないこともあります。
パワーグリップは、手のひらとバーの間にベロ部分がクッションとして介在するため、摩擦や圧迫を大幅に軽減し、マメができるのを防ぎます。
これにより、手のひらの痛みを気にすることなく、目の前のトレーニングに集中できるというメリットが生まれます。
【初心者向け】パワーグリップの正しい使い方を5ステップで解説
パワーグリップの効果を最大限に引き出すためには、正しい付け方と巻き方を習得することが不可欠です。 誤った方法で装着すると、グリップが不安定になったり、手首を痛めたりする原因にもなりかねません。 ここでは、初心者でも迷わずに実践できるよう、パワーグリップの装着からグリップの固定までの基本的な使い方を5つのステップに分けて具体的に解説します。 この方法をマスターすれば、安全かつ効率的にトレーニングの質を高めることが可能です。
ステップ1:左右と向きを確認して手首に装着する
パワーグリップには多くの場合、左右が定められており、製品に「L(Left)」「R(Right)」といった表記があります。 まず、この表記を確認して左右を間違えないようにしましょう。 次に、リストラップ部分のマジックテープを外し、手首に巻きつけます。 このとき、ベロと呼ばれるラバー部分が手のひら側に来るように向きを合わせることが重要です。 ジムでマシンやバーベルの前に立ってから慌てないよう、あらかじめ装着しておくとスムーズです。 締め付け具合は、手首がグラつかない程度にしっかりと、かつ血流を妨げない適度な強さに調整します。
ステップ2:ベロ(滑り止め部分)を手のひらに重ねる
手首に正しく装着できたら、ベロと呼ばれる滑り止め部分を手のひらの上に重ねるように配置します。 このベロがバーベルのシャフトと手のひらの間に挟まり、強力なグリップ力を生み出してくれます。 特に、背中を鍛える代表的な種目である懸垂やラットプルダウンでは、このベロがバーにしっかりと巻き付くことで、握力を消耗することなく広背筋を効かせることに集中できます。 トレーニング動作に入る前に、ベロが手のひらの中心にあり、指の付け根あたりにかかるように位置を調整しておくと、次のステップがスムーズに進みます。
ステップ3:バーやダンベルをベロの上から握る
ベロを手のひらに重ねた状態のまま、トレーニングで使うバーベルやダンベルのバーを握ります。 この段階では、まだベロをバーに巻き込まず、指でバーをしっかりと掴むようにします。 ベントオーバーロウイングなどのローイング系種目では、この時点でグリップ幅や握る位置を最終決定します。
ステップ4:ベロをバーに巻きつけてグリップを固定する
バーを握ったら、もう片方の手や握っている手の指先を使い、ベロの先端をバーの下からくぐらせて、指とバーの間に挟むように巻き込みます。 ベロがバーに1周以上巻き付くように、少し引っ張りながらしっかりと巻きつけるのがポイントです。 この巻き付け作業によって、手のひらとバーが一体化し、まるでバーが手に吸い付くような強力なグリップ力が生まれます。 最初は少し難しく感じるかもしれませんが、数回練習すればすぐに慣れてスムーズにできるようになります。 左右均等にしっかりと巻きつけることを意識してください。
ステップ5:左右のグリップ感を確かめてトレーニング開始
左右両方のパワーグリップをバーに巻きつけ終えたら、トレーニングを開始する前に、一度軽くバーを持ち上げてみましょう。
このとき、左右のグリップ感に差がないか、ベロが緩んでいないか、手首に違和感がないかを確認します。
もし左右の巻き付け具合に違いがあると、トレーニング中にバランスを崩す原因にもなるため、均等な力で握れるように微調整が必要です。
パワーグリップは引く動作で使うため、スクワットなどでは使わない点に注意してください。
パワーグリップの効果を最大化するおすすめ筋トレ種目
パワーグリップは、あらゆるトレーニングで万能なわけではなく、特に「引く動作」、いわゆるプル系の種目でその効果を最大限に発揮します。 握力が先に限界を迎えることで追い込みきれなかった背中や肩のトレーニングにおいて、パワーグリップは絶大なサポート役となります。

デッドリフトやベントオーバーロウなどの背中のバーベル種目
デッドリフトは全身を鍛える非常に効果的な種目ですが、扱う重量が大きいため、背中の筋肉が疲労するよりも先に握力が限界を迎えることが頻繁に起こります。
パワーグリップを使用することで、握力の心配をすることなく、広背筋や脊柱起立筋といったターゲットの筋肉を最後まで追い込めます。
また、ベントオーバーロウは、バーベルを床から引き上げる動作で、広背筋や僧帽筋、菱形筋といった背中の筋肉に厚みを作るための重要な種目です。
この種目も高重量を扱うことが多く、正しいフォームを維持するためには安定したグリップが欠かせません。
パワーグリップを用いて握力を補助することで、腕の余計な力みが抜け、背中の筋肉で引くという感覚、いわゆる「マインドマッスルコネクション」を高めることができます。
懸垂(チンニング)やハンギングレッグレイズなどの自重種目
自重トレーニングである懸垂(チンニング)も、握力の消耗がパフォーマンスを大きく左右するため、パワーグリップが非常に有効です。
また、ぶら下がって腹筋を鍛えるハンギングレッグレイズ
なども握力の消耗を防いだりグリップを安定させ、腹筋・股関節の動きに集中するためにもおすすめと言えます。
【肩の日】シュラッグで僧帽筋に高負荷をかける
シュラッグは、肩をすくめる動作によって首から背中上部にかけて広がる僧帽筋を鍛える種目です。
この種目は、比較的高重量のダンベルやバーベルを保持し続けることが求められるため、握力への依存度が非常に高くなります。
パワーグリップを使用すれば、握力の限界を気にすることなく、本来ターゲットとすべき僧帽筋に最大限の負荷を集中させることが可能です。
これにより、僧帽筋の筋肥大を効果的に促せます。
パワーグリップが不要・効果が薄いトレーニング種目
パワーグリップは多くのプル系種目で非常に役立つギアですが、すべてのトレーニングにおいて有効というわけではありません。特に、バーベルやダンベルを「押す動作」がメインとなるプレス系の種目では、その効果はほとんどなく、むしろ邪魔になることさえあります。
また、握力そのものを鍛えることが目的の場合にも使用は避けるべきです。
特徴を理解し、適切な場面で使うことが、安全で効果的なトレーニングにつながります。
ベンチプレスなどのプレス系(押す動作)種目
ベンチプレス、ショルダープレス、ダンベルプレスといったプレス系の種目は、ウエイトを体から「押して」遠ざける動作が中心です。これらの種目では、バーを強く握り込む力よりも、手首を安定させてブレを防ぐことの方が重要になります。パワーグリップは「引く」動作を補助するために設計されているため、プレス系種目ではその機能を発揮しません。 むしろ、手のひらにあるベロが邪魔になり、グリップを不安定にさせる可能性があります。手首の保護や安定化が目的であれば、パワーグリップではなく「リストストラップ」という専用のギアを使うのが適切です。 リストストラップのように、ギアは目的に応じて使い分ける必要があります。

握力そのものを鍛えたい場合のトレーニング
パワーグリップは握力を補助してくれる便利なギアですが、それに頼りすぎると、握力自体が発達する機会を失ってしまう可能性があります。
前腕を太くしたい、あるいは純粋な握力を強化したいという目的がある場合、パワーグリップの使用は逆効果です。
リストカールやファーマーズウォーク、プレートピンチなど、握力や前腕筋群を直接鍛えるトレーニングを行う際には、パワーグリップを外して、自らの力で重量を保持することが重要です。
自分に合ったパワーグリップの選び方【4つのポイント】
パワーグリップは様々なブランドから多種多様な製品が販売されており、素材やサイズ、形状も異なります。初心者にとっては、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。 自分に合わない製品を選んでしまうと、トレーニングの効率が落ちるだけでなく、手首を痛める原因にもなり得ます。ここでは、後悔しないパワーグリップ選びのために、特に重要となる4つのポイントを解説します。 これらのポイントを押さえることで、自分のレベルや目的に最適な製品を見つけることができます。
ポイント1:滑りにくさを重視するならラバー素材を選ぶ
パワーグリップのグリップ力を大きく左右するのが、バーに直接触れるベロ部分の素材です。主な素材としてはラバー(ゴム)製と革製があります。特に初心者や安定したグリップ感を最優先したい場合には、ラバー素材がおすすめです。ラバーは摩擦係数が高く、バーに吸い付くようにフィットするため、非常に滑りにくいという特徴があります。 一方で、革製のものは耐久性が高く、使い込むほどに手になじむという魅力がありますが、ラバーに比べると滑りやすい傾向にあります。 まずは滑りにくさを重視してラバー素材のものを選び、トレーニングに慣れてから他の素材を検討するのも良いでしょう。
ポイント2:手首の太さに合わせてS・M・Lサイズを選ぶ
パワーグリップは手首に装着して使用するため、サイズ選びが非常に重要です。サイズが合っていないと、適切なサポートが得られなかったり、手首を痛めたりする原因になります。多くの製品は、S・M・Lといったサイズ展開がされており、メーカーごとに対応する手首周りの長さが定められています。 購入前には、必ずメジャーなどで自分の手首の周囲径を正確に測定し、サイズ表と照らし合わせて最適なものを選びましょう。大きすぎると手首で固定できず、小さすぎると血行を妨げる恐れがあるため、ジャストサイズを選ぶことが快適なトレーニングの鍵となります。
ポイント3:ベロは短めだとスムーズに巻きつけやすい
ベロ(タン)の長さも使い勝手を左右する要素の一つです。ベロが長いモデルは、バーに何周も巻きつけることができるため、より強力なホールド力を得られるというメリットがあります。しかし、その分セットアップに時間がかかり、特にインターバルが短いトレーニングでは手間取ることがあります。 一方、ベロが短めのモデルは、バーへの巻き付けが素早く簡単に行えるため、トレーニングのテンポを崩さずにスムーズにセットに入れます。 特に、パワーグリップの扱いにまだ慣れていない初心者や、手軽さを重視する人には、ベロが短めのタイプがおすすめです。
ポイント4:耐久性を求めるなら縫製がしっかりしたものを選ぶ
パワーグリップには常に高重量の負荷がかかるため、耐久性は非常に重要な選定基準です。特に、手首のベルト部分とベロの結合部は最も力が集中する箇所であり、ここの強度が製品の寿命を決めると言っても過言ではありません。安価な製品の中には、この部分の縫製が甘く、すぐにほつれてしまったり、使用中に破れたりするケースも見られます。
パワーグリップは使うべきか否か
パワーグリップは握力の消耗を抑え、正しいフォームでターゲット筋を使いやすくする非常に優れたツールです。しかし、一方で“握力そのものを鍛える機会が減る”という側面も存在します。
実際、50歳以上の女性を対象とした研究では、相対的握力が低い群ほど慢性腰痛の発症リスクが約1.3倍高いと報告されています(Choi et al., 2021)。
握力は「全身筋力の指標」とされるほど、身体全体の筋力状態を反映しやすい項目のため、握力が弱いということは体幹や下肢の支持力低下にもつながり、結果として腰部へ負担が集中しやすくなる可能性があります。
そのため、パワーグリップは“正しいフォーム習得・狙った筋肉に効かせたい場面”では非常に効果的ですが、握力強化を目的とする場合や、体幹・下肢の支持性を向上させたいお客様には、あえて使用しない選択が有効なケースもあります。重要なのは、
・種目の目的は何か?
・機能改善を優先するのか、効かせることを優先するのか?
・負荷が適切に設定されているか?
こうした判断基準を持ったうえで「使う/使わない」を選択することです。
※もちろん、パワーグリップ自体は非常に有用なツールであり、“使うこと=悪”ではありません。目的に応じて賢く使い分けることが大切です。
まとめ
パワーグリップは、握力を補助することでトレーニングの質を向上させる有効なギアです。 主なメリットとして、握力の消耗を防いでターゲットの筋肉を追い込めること、より重い重量を扱えるようになること、手のひらを保護できることが挙げられます。 特にデッドリフトや懸垂といった引く動作の種目で効果を発揮しますが、ベンチプレスなどの押す動作の種目には適していません。 自身のトレーニング目的に合わせて、素材、サイズ、ベロの長さ、耐久性を考慮して適切な製品を選ぶことが大切です。 正しい使い方をマスターし、日々のトレーニングに取り入れることで、筋力向上の効率を高めることができます。
なお、運動効果を高めたい方や自分に合ったトレーニングメニューを詳しく知りたい方は、Dr.トレーニングにご相談ください。
Dr.トレーニングは、採用率3%以下の厳選されたプロトレーナーが、500種類以上のトレーニングメニューから、お客様のご要望にあわせてトレーニングをカスタムメイドするため、効率良くボディメイクができます。
無料カウンセリングや体験トレーニングも実施しているので、気になる方はぜひお問い合わせください。
【著者情報】
東田 雄輔
– 資格
・NSCA-CPT(全米エクササイズ&コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー)
・JATI-ATI(日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者)
・NASM-PES(全米スポーツ医学協会認定パフォーマンス向上スペシャリスト)
・NASM-GFS (全米スポーツ医学アカデミー認定ゴルフフィットネススペシャリスト)
・IASTM SMART TOOLs
・PRI Postural Respiration 修了
・PRI Pelvis Restoration 修了
・PHI pilates act
https://drtraining.jp/cast/higashida/
[参考文献]
Sungwoo Choi et al. “Association between Relative Handgrip Strength and Chronic Lower Back Pain: A Nationwide Cross-Sectional Analysis of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey”,
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8535507/